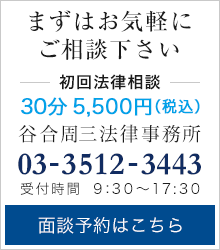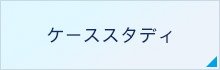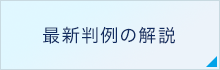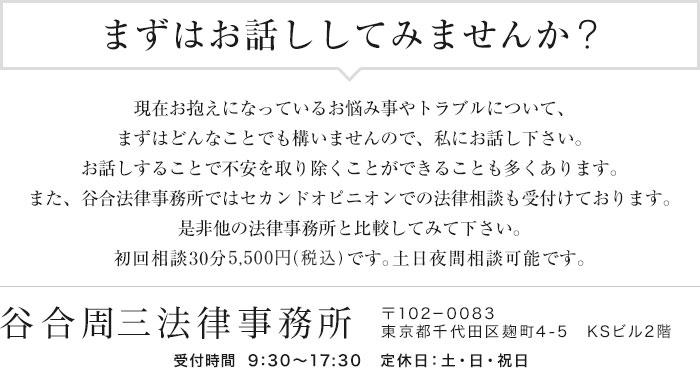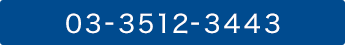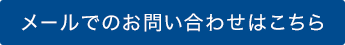相続問題

よくある相談ケース
- 遺産の分割内容について、相続人間の話し合いがまとまらない。
- 相続の手続きや納税の方法が分からない。
- 遺言は、どのような内容でも効力を持つのだろうか。
相続がほかの法律問題と異なる点は、「誰にでも必ず起こり得る」ということです。そして、資産を残す側の思惑とは裏腹に、一定の割合で「争続」へと発展します。円満解決を図ることも重要ですが、大切なのは、トラブルにならないような手だてをあらかじめ整えておくこと。そのためのお手伝いを、弁護士が行います。
弁護士へ相談するメリット
ケース紹介:相続発生前の対策のケース
【ご相談内容】
遺言に興味があり、具体的な相続プランも持っているので、相談に乗ってほしい。
【当事務所の対応】
法定相続人(兄弟姉妹の方々を除きます)には、一定の遺産を譲り受ける権利があり、これを「遺留分」といいます。遺言より効力があるため、「遺留分」を侵害するような内容を残すと、後でトラブルになる可能性があります。そこで当事務所では、不動産評価をはじめとする資産総額を正確にお見積もりし、もめ事の火種にならないようなプランづくりのアドバイスをいたしました。
【結果】
遺言の原案を税理士と相談しながら作成。その後、公証役場へ赴き、「公正証書遺言」が完成した。
【ポイント】
遺言は自筆でもしたためることができますが、一定の要件を満たしていないと、無効と見なされてしまいます。確実に実行されることを望まれるのであれば、遺言のプロが作成する「公正証書遺言」がお勧めです。
ケース紹介:相続発生後の対応のケース
【ご相談内容】
相続の発生をきっかけに、亡父に買ってもらった乗用車や大学の学費負担など、生前に受けた贈与を巡って話し合いが難航。出口が全く見えない。
【当事務所の対応】
相続人それぞれの希望をヒアリングし、土地を望む人、お金を望む人など、それぞれのこだわりを抽出。各自の主張が目に見える形になったところで、最大公約数的な解決案をご提示しました。
【結果】
解決案を元に遺産分割協議書を作成。すべての相続人から署名・なつ印を集め、合意の証とした。
【ポイント】
遺産分割には人の意志が絡むため、単純な割り算がなじみません。関係者の心情に留意しつつ、話し合いを進めていく必要があるでしょう。財産を残す側にも、生前から趣旨を説明すると共に遺言を残し、こうした事態を防ぐことが求められます。もしくは、生前贈与で意思表明を行い、最終的な財産をあまり残さないのも、ひとつの方法といえるでしょう。
相続問題に関する弁護士費用
事件を受任するにあたっては、相手方に対して請求する金額その他の、当該案件における経済的利益の額に応じて、以下の基準に基づいて計算される金額の着手金のお支払いをお願いします。また、現実に経済的利益が得られた場合には、以下の基準に基づいて計算される報酬金のお支払いをお願いします(ただし、着手金・報酬金ともに税込です)。
なお、詳細は、受任にあたっての協議によって決定させていただきます。
経済的利益の額が300万円以下の部分
| 着手金 | 8% |
|---|---|
| 報酬金 | 16% |
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分
| 着手金 | 5% |
|---|---|
| 報酬金 | 10% |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の部分
| 着手金 | 3% |
|---|---|
| 報酬金 | 6% |
経済的利益の額が3億円を超える部分
| 着手金 | 2% |
|---|---|
| 報酬金 | 4% |