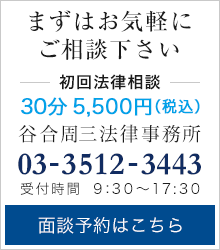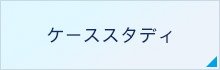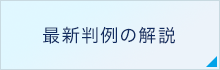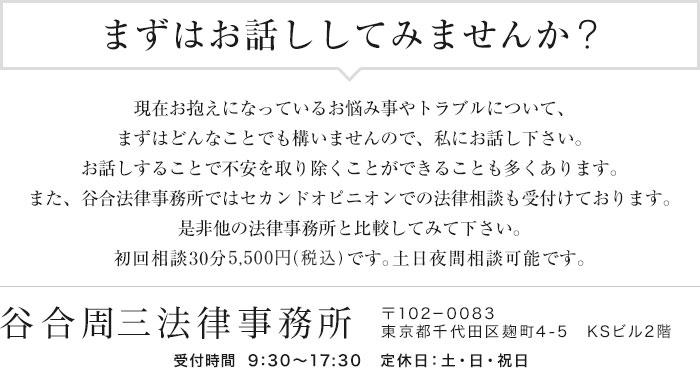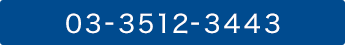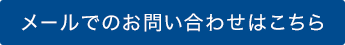不動産トラブル

よくある相談ケース
- 境界や植木の張り出しなどで、隣人ともめている。
- 欠陥を売り主に修復してもらいたいが、契約書に定めた保証期間が過ぎてしまった。
- 原状回復とは、どの程度のことを指すのか。
中古の物件で多いのは、不動産を購入した後に不具合などが発見される、いわゆる「聞いていなかった」というケースです。欠陥などを故意に知らせていなかった場合は、契約書に定めた保証期間が過ぎていたとしても、修復費用などの請求が可能となることもございます。
弁護士へ相談するメリット
ケース紹介:不動産売買のケース①
【ご相談内容】
土地を購入し、新たにアパートを建てようとしたところ、地面の中から大量のコンクリートガラが出現した。売り主に対し、除去費用を請求したい。
【当事務所の対応】
土地の売買契約書を確認したところ、売り主は、瑕疵について責任を負わない旨の特約があることが判明。売り主側は、特約を根拠に費用負担を拒否してきましたので、訴訟を起こすことになりました。
【結果】
こちらのねらいは、責任を負わないとする特約を無効にすることです。売り主は、土地上の旧建物を所有しており、それを撤去して売却したという経緯があったので、売主に対し、旧建物撤去の際に建物の基礎コンクリートなどをどのように取り除いたのか、具体的に立証させる作戦を採りました。経緯を十分に説明できなかった売り主は、ガラの存在を知っていながら売り渡したと判断され、最終的に除去費用の全額負担を命じられました。
【ポイント】
売主が瑕疵や不具合を意図的に秘匿していたことが立証できれば、前提となる特約は効力を持ちません。このケースではうまく立証ができました。
ケース紹介:不動産売買のケース②
【ご相談内容】
自宅の建設用地を購入したところ、隣人から、自分の敷地を侵害しているとのクレームが入った。売買契約を解除し、違約金を請求したい。
【当事務所の対応】
売り主側に事情を確認したところ、隣人との合意は取れているとのことでしたが、「同意書」のような書面は取り交わしていなかったようです。自宅建設を進めることが事実上不可能となったため、違約金の支払いを求めましたが、売り主は「隣人に非がある」として、これに応じようとはしません。そこで、訴訟を起こすことになりました。
【結果】
係争と平行して話し合いを続けた結果、違約金を減額することで和解がなされ、スピード解決に至りました。
【ポイント】
裁判での決着は長期化が予想されたため、ご依頼人の同意を得た上で、落としどころを模索したケースです。
ケース紹介:未払い家賃の回収・強制退去のケース
【ご相談内容】
アパートの借り主が家賃を滞納し、このままだと敷金による補てん額を超えそうなので、早急に何とかしたい。
【当事務所の対応】
借り主には家賃を継続して支払う能力がなかったため、任意退去を迫りました。
【結果】
家賃の未納分は、住人の保証人に請求し、無事支払いを得ることができました。
【ポイント】
家賃の滞納が3カ月を越えたら、支払いを求めるよりも、新しい借り主を探した方が、損失を少なくできる可能性が高いと思います。手をこまねいているだけでは、いたずらに不利益を積み重ねてしまいます。この場合、強制執行の手続き取ることも可能ですが、その費用は一時的に大家側が負担することになります。家賃を滞納している相手からその費用を取り立てるのが現実的に難しいことを考えると、任意交渉を行うのが、もっともスムーズな方法といえるのではないでしょうか。
不動産トラブルに関する弁護士費用
事件を受任するにあたっては、相手方に対して請求する金額その他の、当該案件における経済的利益の額に応じて、以下の基準に基づいて計算される金額の着手金のお支払いをお願いします。また、現実に経済的利益が得られた場合には、以下の基準に基づいて計算される報酬金のお支払いをお願いします(ただし、着手金・報酬金ともに税込です)。
なお、詳細は、受任にあたっての協議によって決定させていただきます。
経済的利益の額が300万円以下の部分
| 着手金 | 8% |
|---|---|
| 報酬金 | 16% |
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分
| 着手金 | 5% |
|---|---|
| 報酬金 | 10% |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の部分
| 着手金 | 3% |
|---|---|
| 報酬金 | 6% |
経済的利益の額が3億円を超える部分
| 着手金 | 2% |
|---|---|
| 報酬金 | 4% |